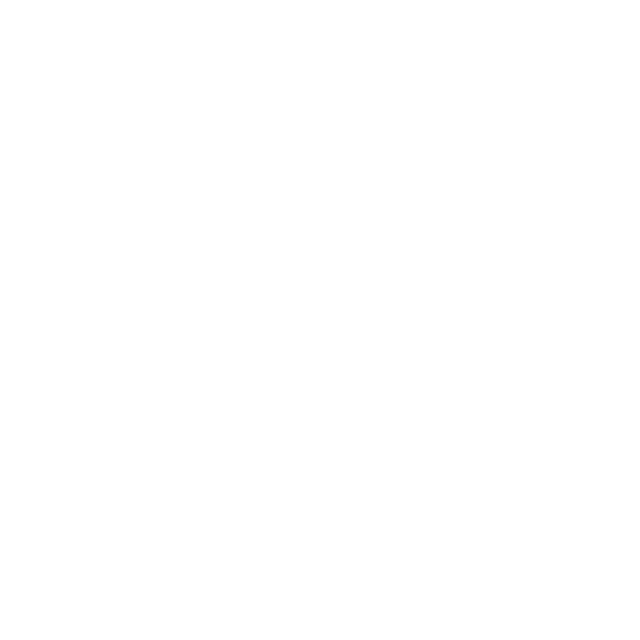神崎酒造
姫路藩の歴史の中で、丁寧に守り継ぐのは
地元密着の地酒、毎日の晩酌で愛でられる味。
ずっしりとした酒蔵に酒造りの歴史を感じますね。

「地元の文化や風土に密着した日本酒造り」
がモットーと語るのは、岡庭昭八郎代表取締役
私どもの先祖はもともと上州の出身です。
江戸時代のお国換えで殿さまと一緒に姫路藩にやってきました。
ところがすぐに酒造りを始めたわけではなく、江戸時代後期の財政難の頃、姫路藩が何か手を打たねばと始めた高麗人参の栽培と薬作りがそもそもの生業。
この地は「西光寺野人参役所跡(岡庭家)」という名で、姫路藩の歴史を伝える場所として知られています。
その人参役所は明治4年に大きな百姓一揆が起こって焼失。その後、明治8年に播磨地域の酒米を利用して、郡内では初めて、酒造業をスタートさせました。
現在も使っている蔵のうち、一番古いものはこの時に建てられたと聞いております。
当時は「岡庭」の苗字で「岡庭酒造店」として看板をあげていました。
その後、酒造りは順調だったのですが、昭和の終戦の頃、食糧難による行政指導により廃業を経験。戦後、同じ地区にあった3蔵で「神崎酒造」として再スタートし、現在に至ります。
時代に翻弄されながらも、地元の酒を造り続けてきました。
「真名井乃鶴」「龍王の舞」が代表的な銘柄ですね。

歴史を感じさせる貯蔵蔵には、
地元への想いがこもった酒が静かに眠っている
小さな酒蔵ですので、銘柄も絞り込んで作っております。
きれいな水の沸く泉という意味のある「真名井」に降り立つ天女をイメージした「真名井乃鶴」は、すっきりとさわやかな味。
優雅でまろやかな口当たりは、降り立つ鶴のようにと思いながら作らせてもらっています。
毎日の晩酌で楽しんでもらえる飽きのこないお酒で、代々造り続けてきた一品です。
一方の「龍王の舞」は、平成に入って私が作り出したもので、五穀豊穣を祈願する播磨地域のお祭りに奉納する舞にちなんだお酒。
辛口のさわやかな飲み口で、祭りの宴席で盃を酌み交わしながら、豊かな時間を過ごしてほしいと思っております。
どちらも和食に合う味です。郷土の文化に根差した酒造りを通して、地元の人たちの生活が豊かになってくれればうれしいですね。
播磨の歴史にちなんだ「銀の馬車道」という商品もあるんですね。

敷地内にある小さなほこら。
酒造りをずっと見守ってきた神さまだ。
弊社の前の道は「銀の馬車道」と呼ばれておりまして、明治初期、兵庫県朝来市生野地域から姫路港までの49kmを馬車が銀を運んだ、国内初の高速産業道路だったのです。
現在は、沿道の地域が協力して、当時の面影を感じながら各地を回る観光ルートとして、もりあげようとがんばっています。
こういった取り組みに、弊社として何かできないかと作ったのが「銀の馬車道」という商品。
地域振興の取り組みとともに、播磨の酒が広がってくれるといいですね。
これからの取り組みについてはいかがですか?

私たちが作っているのは播磨の地酒。
「地酒」は地域の文化に一番合う味ですから、地元の人に愛されるものでないといけません。
思いをこめて造ったおいしい地酒を地元の人にたくさん飲んでもらいたいですね。
最近では直接酒蔵まで買いに来てくださるお客様も増えてうれしく思っています。
これからも自分たちが目の届く範囲で大切に酒造りをしていきたいと思っています。