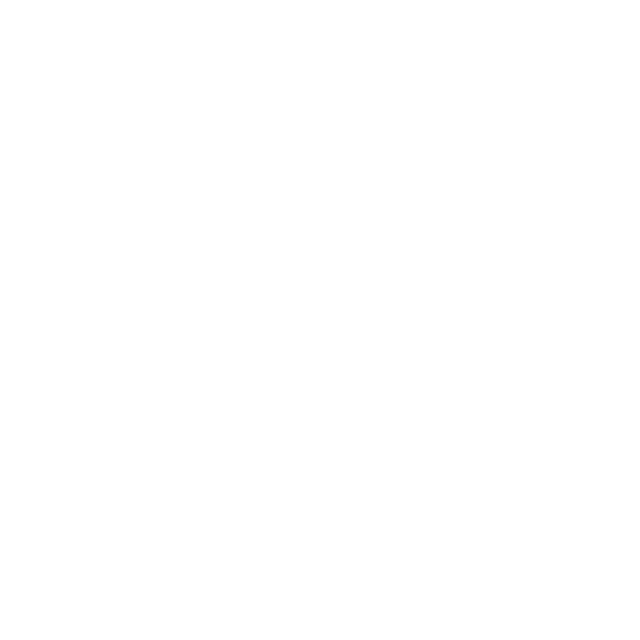奥藤商事
歴史深い忠臣蔵の地、赤穂の港町で400年、
昔ながらの製法に受けつがれる手作りの心。
風情のある昔ながらの町並みが残る場所ですね。

酒造業を継ぐ前は、
まったくの異業種だったという
奥藤利文代表取締役。
その経験が酒造りにも生きている
このあたりは幕末から明治の頃、赤穂の名産品である塩の積み出し港として栄えていました。
奥藤家は廻船業などで財を築いた地元の庄屋でして、酒造りを始めたのは慶長6年(1601年)のことです。
かつては赤穂藩主浅野家の御用酒屋でした。当時の酒造りに関するおもしろい言い伝えもあるんですよ。
「ある日、どこからともなくやってきた白髪のご老人に、主人がお茶を出しますと、その老人は何も言わずに、米俵と元柄杓(ひしゃく)をおいて出て行ったとか。その米俵と元柄杓を見た主人が、『これは酒造りをしろということに違いない』と思い、始めた」
と言われております。
現在、敷地内に観光で来られた方のために酒造郷土館を作っているのですが、言い伝えの米俵と元柄杓の実物もそこで見ていただくことができます。
また一番古い酒蔵は300年以上前のものですし、坂越の街並みと同様に往時の雰囲気を感じてもらえると思います。
400年続く酒造りの名家、こだわりはどんなところにありますか?

昔ながらの町並みが観光客に喜ばれる坂越地区。
赤穂藩の歴史のなかで活躍してきた酒蔵だ
以前は蔵人さんに何人も来てもらっていましたが、現在は私と若い蔵人の2人で仕込んでいます。
私はもともと、異業種で仕事をしていたこともあって、最初の頃は手探りでした。
うちに来ていた蔵人さんに直接教えてもらったり、播磨地区の酒蔵の先輩たちにいろいろと手ほどきやアドバイスをもらったりして、うちらしい味を追求してきました。
こだわっているのは、昔ながらの手造りというところですね。
清流千種川の水に、播磨の酒米という日本酒に最適な素材を使って、昔ながらの丁寧な作り方をしています。
赤穂といえば忠臣蔵ですが、うちの代表的な銘柄も「忠臣蔵」。
忠誠心の厚かった浪士のように、手造りのよさが味に出てくるよう大切に作っています。
現在、赤穂の蔵元はうちだけ。赤穂の酒として、日本全国の人に飲んで、うまいと感じてもらいたいですね。
忠臣蔵シリーズの魅力はどんなところでしょう。

敷地内の酒造郷土館に展示されている、
伝承の柄杓と米俵。
奥藤の酒造りを見守ってきたご神体
私たちが目指すのは、淡麗辛口のようにさらっと飲めるお酒よりも、「飲みごたえ」のある豊かな味わいがあるもの。
アルコール度数が高めでガツンとボリュームあって、それでも「もう一杯」と言いたくなる後味のよさ...、そんなお酒を目指しております。
大吟醸、純米吟醸、山廃純米とありますが、深みがあって細やかな味ですよ。
忠臣蔵シリーズによく合うのは、同じように細やかな味のする瀬戸内の魚介ですね。
蔵のある坂越地区はカキの養殖が盛んなところですから、やっぱりカキにあわせてもらいたい。
酢ガキ、焼きガキはおすすめです。
姫路の名物、アナゴの白焼きなんかにも、うちの日本酒は最高に合うんじゃないでしょうか。
地元産のお米でも酒造りをされているそうですね。

潮風の強い赤穂の風土に醸される日本酒は、
細やかな味の瀬戸内の魚介類によく合うという
最近は県立上郡高校農業科の生徒さんが作ったお米で、お酒を仕込みましたね。
高校の生徒さんが何人かインターンシップで、酒造りの体験にも来ました。
米を洗ったり、仕込んだり、絞ったりと日本酒作りの工程を一緒にすることで、生徒さんも何か感じてくれたのではないかと思っています。
私たちは地元でずっと事業を続けさせてもらっていますから、地元のためになる活動で恩返しができればいいなと思いますね。
地酒は酒造りそのものを続けていくことが大切。歴史のある蔵で手作りにこだわって造ることで、地域の味として育つと思います。
今は出荷量も少ないですが、これからもっと増やせるようにがんばっていきたいですし、日本中の多くの人にうちの酒を「赤穂の酒」として楽しんでもらえるように、酒蔵を守っていきたいと思っています。
おすすめ商品紹介
-
山廃仕込み 純米 忠臣蔵

酒母を山廃仕込みにした昔ながらの製法。厚みのある味わいと、コシの強さを堪能して。
-
忠臣蔵 純米吟醸

山田錦を55%に精米し、丁寧に仕込んだ、なめらかでやわらかな日本酒本来の味わい。
-
大吟醸 忠臣蔵

華やかな香りをはなつ上品な味わいは、40%まで精米した山田錦と蔵人の手間がなせる技。
奥藤商事 概要

| 会社名 | 奥藤商事株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒678-0172 兵庫県赤穂市坂越1419-1 |
| TEL | 0791-48-8005 |
| FAX | 0791-48-8813 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 日曜、祝日 |
| 駐車場 | 10台 |
| 蔵見学 | 蔵内はできませんが、 酒造郷土館の見学は無料にて行っています。 |
| 酒の入手方法 | 蔵内の販売所、FAX注文 |
| 試飲 | あり |