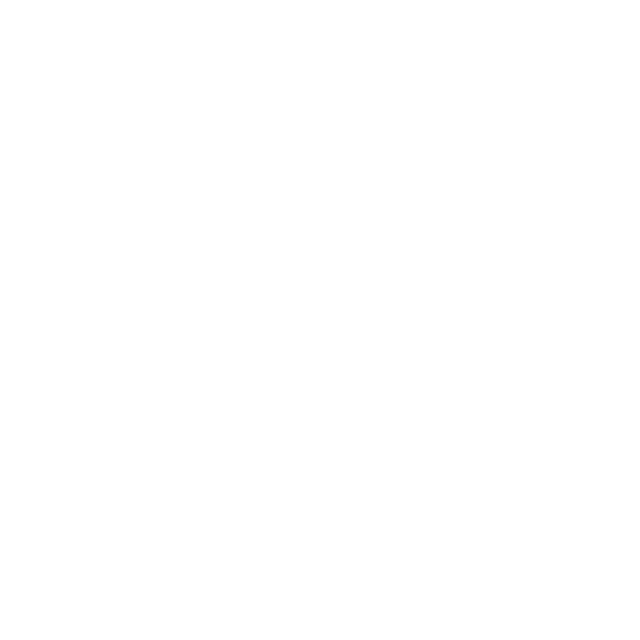田中酒造場
伝統の酒造りを、未来ある形で後世へ、
地元農家とともに新たな酒造りを目指す挑戦者。
酒造りに「温故創新」のモットーを掲げられていますよね。

常に業界の先を見て、チャレンジを続けてきた
6代目の田中康博社長
弊社は天保6年(1835年)に創業し、姫路の酒蔵として「名刀正宗」という銘柄を主に造り続けてきました。
その一方で、姫路の政治にも深く関わり、3代目は戦後すぐの内閣で運輸大臣に就任しました。
私で6代目ですが、現在は本業の酒造り一筋で邁進しています。
私は30歳で帰郷して、家業に加わった後、全国の有名な酒蔵を行脚しながら、
酒作りの研究を続けました。今までに50~60カ所は回ったでしょうか。
元来、好奇心旺盛な性格でして、普段から多種多様な情報をキャッチして、
自分なりにアレンジし、引き出しを増やしていることが、新たな酒造りのカギになっているように思います。
「温故知新」の「知る」にとどまらず、作り手として新しく「創る」にこだわることが、
私の喜び。
日本人の魂に響く日本酒を、今の時代にあった味で創りだす「温故創新」の思いのもと、
5年、10年先の酒造業界を見すえた酒造りを続けています。
伝統の「石掛け式天秤搾り」は、年末の地元の風物詩としても有名になりました。

伝統の手法と機械式のメリットを融合して、
オリジナルの造り方を追求している
新酒の初搾りとして、マスコミの皆さんにも取り上げてもらっています。
「石掛け式天秤搾り」はもろみを絞る方法としては最も古いとされていますが、当蔵でもずっと行っていたわけではありません。
21世紀を前に日本の文化、伝統の酒造りを後世に伝えていきたいと思い、
アイデアを探していたところに、蔵の中に道具が残っていたのです。
それを見た瞬間に「これだ!!」と感じ、平成12年に復活させました。
現在、この搾り方を採用している蔵元は少ないのですが、
結果として機械式にはないまろやかな酒に仕上がるのです。
昔の人は機械を使わずとも、緻密な細工で、実にうまい酒を造る方法を知っていたのだと感服する手法のひとつです。
日本酒は複雑な工程を経て仕上がる特別な酒。
こだわるポイントはたくさんありますし、それによって香りも味もぜんぜん違ってくる。チャレンジのしがいのある相手です。
「大吟醸 白鷺の城」は全国新酒鑑評会でよく金賞を受賞していますよね。

どのラインナップにも並々ならぬこだわりを見せ、
受賞経験豊富な商品が多い
昭和63年に初めて受賞して、それから7年連続受賞、
通算では17回受賞させてもらいました。
綺麗ですっきりとした繊細な味だと思います。
また亀の尾という希少な酒米を磨き上げて仕込んだ「亀の甲」という日本酒も話題を呼びました。
精米技術をとことんまで極めて醸しており、現在は精米歩合8%まで達しています。
これだけ磨いた米を一般的な吟醸酒と同じように仕込んだら、だいたいは苦みや渋みが強くなる。他ではなかなか出せない味だと思いますよ。
ここまでこだわった日本酒は、到底、蔵の力だけではできません。
お米を作ってくれる農家さん、精米技術を磨いてくれる業者さん、
皆さんと一緒に作ったお酒です。
採算は度外視ですが、「お酒にもっと興味をもってもらいたい」という宣伝のためにもチャレンジしています。
最近は農家の方と一緒に、酒米の栽培をしているそうですね。

蔵人や農家、業者...、
それぞれの酒造りの想いを一緒に仕込んだ日本酒が眠る
酒を造って売るだけが造り酒屋じゃないと思っています。
「ストーリーのある酒を造りたい」と考えて「地酒」の意味を追求すると、
地元産のお米、播磨産のお米で作った、安心で安全な日本酒にたどりつくのです。
今は契約農家さんと一緒に、田んぼの土壌作りから理想を追求しているところ。
山田錦より栽培が難しい米にチャレンジしているので、私の要求は難しいかもしれません。
他の地域の米作りのプロにアドバイスをいただきながら、農家さんと本気で意見を出し合いながら取り組んでいます。
将来的には「○○さんの田んぼで採れた米」と表示するのが、
日本酒のスタンダードになるくらいにしたい。
蔵元や蔵人だけでなく、農家の顔も見える酒造りをしたいと思っています。
その方が農家の方も張り合いが出ますし、広い意味で地酒業界が活性化するはず。
全国の造り酒屋には、平均しても200年以上の歴史がある。
それを後世に未来のある形で引き継いでいけるよう、これからも努力していきたいと思っています。